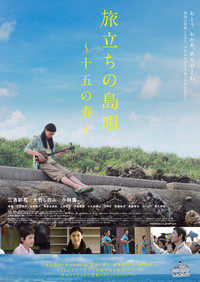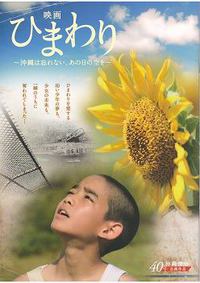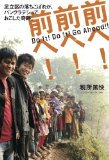2008年02月25日
講師は軍事マニアその2
2月23日 軍都廣島の過去と現在をフィールドワークした。
 講師はいつもの軍事マニア。
講師はいつもの軍事マニア。
今回も怪しいブツが用意される。
「8・6」前の広島はどんな街かというと、それはまぎれもない「軍都」としての廣島でした。日本の対外侵略戦争のエスカレートと歩調を合わせて発展した歴史を持っています。
広島の軍都化は、日清戦争をきっかけとして始まり、その後第二次世界大戦終結までの約50年間、いずれの対外戦争においても重要な前進基地・補給基地としての役割を果たしました。その間、広島には大本営の設置など次々と軍事施設が増設され、宇品港からは数知れない多くの兵士・武器・軍需品が積み出されました。

陸軍墓地から宇品方面を望む。(左矢印が被服支廠、右矢印は似島)
被服支廠:軍服、軍靴、軍帽その他兵隊が身に着ける小物や付属品を生産・修理・保管・供給していました。被爆遺跡としても有名で、今残っている建物は3棟だけですが、当時は98棟ありました。
その他、宇品には兵士の食糧(缶詰など)を製造する糧秣支廠、霞町に兵器支廠があり、軍都廣島は戦争のための兵器、衣類、そして食糧が生産される場となっていました。
似島:日清戦争後兵士が戦地から持ち帰った為かコレラが大流行しました。そのため陸軍はここに検閲所を第二次世界大戦終了直後まで設置しました。戦地から帰ってきた兵士が数日間ここで健康診断や消毒風呂に入るなどの検閲を受け異常のない兵士達のみ本土に帰っていきました。
広島は兵士の出征だけでなく帰還の地にもなっていました。
午後はこれまた怪しい軍事マニアの解説にて海上から基地視察を行う。

宇品港にてノムの宮に見送られながら呉湾へ
広島の周辺の瀬戸内海は、岩国の米軍基地、海田の陸上自衛隊、呉の海上自衛隊と自衛隊や米軍施設がひっきりなしにあります。
呉港は明治維新以降、軍港として発展し、戦後、米軍に接収された後返還され、海上自衛隊や、石川島播磨、海上保安庁として使用しています。
基地としては瀬戸内海の地理より外洋に出るまで時間がかかるという面があり、主に燃料貯蔵庫や弾薬補給基地、術科学校などの教育施設といった後方支援としての性格を持ってます。
平和都市ヒロシマといいながらも、その周辺には米軍基地、自衛隊、軍需産業に取り囲まれ「軍に依存せざるをえない地域の体質」も現実としてあるのです。
基地があることによる潤いはしょせんバブルでしかなく、本来は基地がなくとも自立できる街として地場産業を発展させるというのが行政の役割ですが、その道を選ぼうとすると相当な荊の道が用意されるというのも現実としてあります。
現実を知り見極め冷静に立ち向かうための力を蓄えていくことが必要です。
今回も怪しいブツが用意される。
「8・6」前の広島はどんな街かというと、それはまぎれもない「軍都」としての廣島でした。日本の対外侵略戦争のエスカレートと歩調を合わせて発展した歴史を持っています。
広島の軍都化は、日清戦争をきっかけとして始まり、その後第二次世界大戦終結までの約50年間、いずれの対外戦争においても重要な前進基地・補給基地としての役割を果たしました。その間、広島には大本営の設置など次々と軍事施設が増設され、宇品港からは数知れない多くの兵士・武器・軍需品が積み出されました。
陸軍墓地から宇品方面を望む。(左矢印が被服支廠、右矢印は似島)
被服支廠:軍服、軍靴、軍帽その他兵隊が身に着ける小物や付属品を生産・修理・保管・供給していました。被爆遺跡としても有名で、今残っている建物は3棟だけですが、当時は98棟ありました。
その他、宇品には兵士の食糧(缶詰など)を製造する糧秣支廠、霞町に兵器支廠があり、軍都廣島は戦争のための兵器、衣類、そして食糧が生産される場となっていました。
似島:日清戦争後兵士が戦地から持ち帰った為かコレラが大流行しました。そのため陸軍はここに検閲所を第二次世界大戦終了直後まで設置しました。戦地から帰ってきた兵士が数日間ここで健康診断や消毒風呂に入るなどの検閲を受け異常のない兵士達のみ本土に帰っていきました。
広島は兵士の出征だけでなく帰還の地にもなっていました。
午後はこれまた怪しい軍事マニアの解説にて海上から基地視察を行う。
宇品港にてノムの宮に見送られながら呉湾へ
広島の周辺の瀬戸内海は、岩国の米軍基地、海田の陸上自衛隊、呉の海上自衛隊と自衛隊や米軍施設がひっきりなしにあります。
呉港は明治維新以降、軍港として発展し、戦後、米軍に接収された後返還され、海上自衛隊や、石川島播磨、海上保安庁として使用しています。
基地としては瀬戸内海の地理より外洋に出るまで時間がかかるという面があり、主に燃料貯蔵庫や弾薬補給基地、術科学校などの教育施設といった後方支援としての性格を持ってます。
平和都市ヒロシマといいながらも、その周辺には米軍基地、自衛隊、軍需産業に取り囲まれ「軍に依存せざるをえない地域の体質」も現実としてあるのです。
基地があることによる潤いはしょせんバブルでしかなく、本来は基地がなくとも自立できる街として地場産業を発展させるというのが行政の役割ですが、その道を選ぼうとすると相当な荊の道が用意されるというのも現実としてあります。
現実を知り見極め冷静に立ち向かうための力を蓄えていくことが必要です。
Posted by tana at 23:11│Comments(0)
│日記のようなもの’08