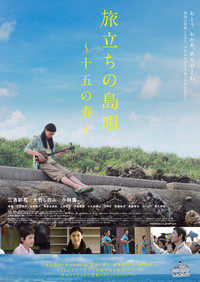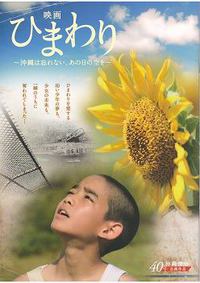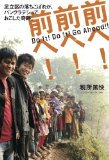2006年01月22日
「沖縄は基地を拒絶する」より
まぁ本の中身ははっきり言ってありきたりの主張が繰り返されている。
しかし、その中で、私の心にグサリと刺さるような文章があった。
しかし、その中で、私の心にグサリと刺さるような文章があった。
「日本に住む人たちは沖縄に住む私たちに励ましの声はかけるけど、自分は安全地帯にいて代わろうとは言わないじゃないか。」
「ヤマトの土地でそれぞれができることをしてください。」
「沖縄に闘いに来なくていいから、あなたが住んでいる土地で、日本人を変えることを考えてください。」
政府やメディアに対する件は「誰かの背後に隠れ同じ立場」で、なんというかある種「心地よく」読めるが、この文章に対しては、一種の戸惑いとともにここまでスコーンといわれ改めて自分に降りかかっている問題であることを実感する。
過去、沖縄(琉球)は日本(薩摩)に侵略され、戦前まで差別的な扱いを受けた。
60年前、日本は沖縄を見捨て、沖縄はアメリカのものとなった。
日本の一部に戻ってからも都合よく「アメとムチ」を使い分けられ続けている。
日本で(例えば岩国で)基地の増強反対を言っている人は、
そういうものは沖縄に押し付けておけばいい、自分達のところが騒音被害を受けなければいい、そういうことなのだろうか?それとももっと大きなところから見て反対を言ってるのだろうか?
いっそ、東京湾や瀬戸内海を埋め立てて米軍基地を造ればいい。
平和ボケして刺激がほしい人たちにはちょうどいいのでは?
経済発展にもなるのでは?
そういう考えは生まれないのだろうか?
沖縄に行くたびに思うのは、ここはまだ沖縄戦が続いてるんだなってこと。
・・・つづく
「ヤマトの土地でそれぞれができることをしてください。」
「沖縄に闘いに来なくていいから、あなたが住んでいる土地で、日本人を変えることを考えてください。」
政府やメディアに対する件は「誰かの背後に隠れ同じ立場」で、なんというかある種「心地よく」読めるが、この文章に対しては、一種の戸惑いとともにここまでスコーンといわれ改めて自分に降りかかっている問題であることを実感する。
過去、沖縄(琉球)は日本(薩摩)に侵略され、戦前まで差別的な扱いを受けた。
60年前、日本は沖縄を見捨て、沖縄はアメリカのものとなった。
日本の一部に戻ってからも都合よく「アメとムチ」を使い分けられ続けている。
日本で(例えば岩国で)基地の増強反対を言っている人は、
そういうものは沖縄に押し付けておけばいい、自分達のところが騒音被害を受けなければいい、そういうことなのだろうか?それとももっと大きなところから見て反対を言ってるのだろうか?
いっそ、東京湾や瀬戸内海を埋め立てて米軍基地を造ればいい。
平和ボケして刺激がほしい人たちにはちょうどいいのでは?
経済発展にもなるのでは?
そういう考えは生まれないのだろうか?
沖縄に行くたびに思うのは、ここはまだ沖縄戦が続いてるんだなってこと。
・・・つづく
Posted by tana at 23:26│Comments(6)
│沖縄戦がらみ
この記事へのコメント
おお!この本!
昨年暮れだったかな、新聞広告で見て、興味をもっていました。
(手元にその広告の切り抜きもあるのですが・・・^^;)
私は、アメリカ軍が日本に基地を置くこと自体に反対です。
沖縄、岩国、横須賀だけじゃなく、『日本は基地を拒絶する』でありたいです。
続きを楽しみにしています^^
昨年暮れだったかな、新聞広告で見て、興味をもっていました。
(手元にその広告の切り抜きもあるのですが・・・^^;)
私は、アメリカ軍が日本に基地を置くこと自体に反対です。
沖縄、岩国、横須賀だけじゃなく、『日本は基地を拒絶する』でありたいです。
続きを楽しみにしています^^
Posted by たなかよ at 2006年01月24日 13:42
この本、パレットくもじの6F(だったかな?)の本屋に山積みされてました。
沖縄本コーナーも充実してるし、そこだけで十分半日は居ることができます。
『日本は基地を拒絶する』でありたいですね。
この記事では、辺野古に基地をつくるのも、瀬戸内海に基地をつくるもの同じことだって意識を示しました^^
沖縄本コーナーも充実してるし、そこだけで十分半日は居ることができます。
『日本は基地を拒絶する』でありたいですね。
この記事では、辺野古に基地をつくるのも、瀬戸内海に基地をつくるもの同じことだって意識を示しました^^
Posted by tana at 2006年01月24日 22:41
ぜひ,「けーし風」(季刊誌)も読んでみてください。
Posted by 長男 at 2006年01月24日 22:57
日本軍は沖縄県民を見捨ててはいませんよ。
軍は昭和19年のうちから沖縄各島への連合軍上陸を警戒して本島北部への避難指示とそれに伴う行政対応を命令していたにも係わらず、沖縄住民が指示に従わないで避難しなかっただけです。
まあ逃げろといわれているのに逃げ無いと言うのは脳天気な沖縄県民らしいですけどね。
例えるならば今の沖縄県民は、隣の家が火事になって消防隊員が燃え移るから逃げろと言ってるにも係わらず避難せず、それでいて火事で焼け出されて家族が死んだら「家族が死んだのは消防隊員の消火活動が疎かだったからだ!!」と怒ってるようなものです。
軍は昭和19年のうちから沖縄各島への連合軍上陸を警戒して本島北部への避難指示とそれに伴う行政対応を命令していたにも係わらず、沖縄住民が指示に従わないで避難しなかっただけです。
まあ逃げろといわれているのに逃げ無いと言うのは脳天気な沖縄県民らしいですけどね。
例えるならば今の沖縄県民は、隣の家が火事になって消防隊員が燃え移るから逃げろと言ってるにも係わらず避難せず、それでいて火事で焼け出されて家族が死んだら「家族が死んだのは消防隊員の消火活動が疎かだったからだ!!」と怒ってるようなものです。
Posted by 凌 at 2006年01月25日 15:46
軍の北部への避難指示と同時に15~60歳までの健康な男性は軍に動員されました。残った人の疎開先に指定された本島北部は日本軍の防衛が手薄な地域だったようで、この中で米軍が上陸すれば当時の日本人の考えでは死を意味するところへの避難勧告でした。
「非戦闘員は殺さない」ことが住民にも県にも軍にも徹底されていなかったようです。そういう状態になるのが戦争状態というものなのでしょう。
まぁ沖縄での日本軍の戦闘力云々よりもこれまでの戦いでアメリカとの戦力の差を見極められず続けてしまったことが、中段にある「沖縄を見捨てた」という意味なのです。
「非戦闘員は殺さない」ことが住民にも県にも軍にも徹底されていなかったようです。そういう状態になるのが戦争状態というものなのでしょう。
まぁ沖縄での日本軍の戦闘力云々よりもこれまでの戦いでアメリカとの戦力の差を見極められず続けてしまったことが、中段にある「沖縄を見捨てた」という意味なのです。
Posted by tana at 2006年01月25日 20:37
たしかに,昭和19年7月7日緊急閣議において,沖縄作戦方面からの老幼婦女子を本土と台湾への疎開が決定され,県知事に通達された。(ただし,法的には強制ではなく勧奨の形であった)
県内疎開は沖縄第32軍より,60歳以上の老人,国民学校以下の小児を20年3月までに北部への疎開,その他の非戦闘員は軍の判断による北部疎開が県当局に要請(命令ではない)されている。
しかしながら,北部に疎開といわれても,北部は住民居住地域,耕作地域が少なく,疎開しても,住むところ,食べるものがないのが実態。軍に言わせれば「軍は敵軍との戦闘のためにあり,住民のためではない」旨の長参謀長の発言のとおり,疎開先の食料などの手当はまったくしないなど,沖縄県民保護を念頭には置いていない。
要するに,戦闘地域における足手まといを北部に移動させるのが目的であったと思われます。なにより,戦闘員として使える青年男子については,疎開対象になっていません。
現に,北部に疎開した約5万人のうち,約2万人が飢えと病気で死んだと言われています。
住民にとって,食・住が保障されていない北部より,「軍民一体」「無敵皇軍」と普段から豪語する友軍とともにいることが,一番安全と判断されたのでしょう。
そういう面では,沖縄の住民は疎開しなかった,というより,疎開先が疎開できない状態であり,疎開しないほうが安全との発想で居住地にとどまったと見るべきでしょう。
(参考,防衛庁防衛研究所戦史室著「沖縄方面陸軍作戦」,藤原彰著「沖縄戦」など)
県内疎開は沖縄第32軍より,60歳以上の老人,国民学校以下の小児を20年3月までに北部への疎開,その他の非戦闘員は軍の判断による北部疎開が県当局に要請(命令ではない)されている。
しかしながら,北部に疎開といわれても,北部は住民居住地域,耕作地域が少なく,疎開しても,住むところ,食べるものがないのが実態。軍に言わせれば「軍は敵軍との戦闘のためにあり,住民のためではない」旨の長参謀長の発言のとおり,疎開先の食料などの手当はまったくしないなど,沖縄県民保護を念頭には置いていない。
要するに,戦闘地域における足手まといを北部に移動させるのが目的であったと思われます。なにより,戦闘員として使える青年男子については,疎開対象になっていません。
現に,北部に疎開した約5万人のうち,約2万人が飢えと病気で死んだと言われています。
住民にとって,食・住が保障されていない北部より,「軍民一体」「無敵皇軍」と普段から豪語する友軍とともにいることが,一番安全と判断されたのでしょう。
そういう面では,沖縄の住民は疎開しなかった,というより,疎開先が疎開できない状態であり,疎開しないほうが安全との発想で居住地にとどまったと見るべきでしょう。
(参考,防衛庁防衛研究所戦史室著「沖縄方面陸軍作戦」,藤原彰著「沖縄戦」など)
Posted by 長男 at 2006年01月26日 00:27