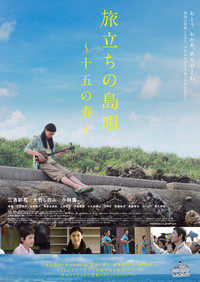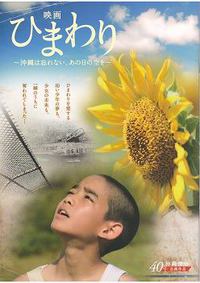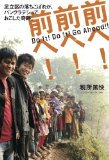2010年11月04日
南大東島へ⑨いよいよ3日目
11月5日(金)南大東3日目
7:00過ぎ起床。
やや昨日の酒が残っている。結局、今日も朝日は見にいけなかった。。。

8:00
朝を軽く食べ、気象台へ行く。
台風の時に良く聞く南大東島。
ここの気象台は台風観測の最前線であるとともに、高層気象観測を行っている。
高層気象観測とは高度約30km付近(成層圏)までの気圧、気温、風光、風速を観測するもの。ここから得られたデータにより高層天気図を作成し天気予報に利用したりしている。こういった観測所は日本国内では16か所、全世界には約900か所あるという。
観測方法は気球に水素ガスを充填させ、空へ飛ばす。気球に付けたセンサーで観測し情報を送ってくるという仕組み。1日に2回、8:30と20:30に観測しているという。気球を飛ばすのは自動化されているので、人手は気球の補充くらいしかいらないという。


水素ガスが入る前の気球 センサー
と、いった説明を気象台の人に受け、さぁ観測時間(気球が飛び出す時間)の8:30になった。

8:30
気球がポンと飛び出し、一気に飛んでいく。あっという間に空の彼方へ飛んでいった。
気象台の近くにあった、ふるさと文化センター(入館料200円)に入る。
この島はその昔、島全体が製糖会社の社有地だったということは知っていたが、以下のような土地問題があったことを初めて知った。
=========================
南大東の土地問題~土地所有者認定記念之碑より抜粋~
本村の農地は、明治33年以来、国有地であった原生林を玉置商会が借り受け、同商会と開拓農民との間に貸付期間満了後は農民に所有権が払い下げられるとの口約で、前人未到の地に、農民の自力自費を投じて指南にして崇高な開拓がすすめられ、大将の初期には全農地が開拓された。
大正5年、経営不振に陥った玉置商会は、事業権を東洋製糖株式会社に売り渡し、諸々の経緯を経て東洋製糖会社は土地の所有権も取得した。しかし昭和3年、同社は大日本製糖株式会社に合併されたため、南大東島は大日本製糖株式会社の所有地となった。結果、島は位置会社が経営支配するという日本国中に前例のない社会制度が昭和21年まで続いた。
昭和26年、農地の所有権は開拓農民およびその後継者にあるという先の事実に基づき、村長以下全村民が団結して、土地所有権認定問題を関係当局に提起。会社とも折衝を重ねたが、島の支配者も変転されているだけに困難を極めた。昭和36年6月、時の琉球列島高等弁務官キャラウェイ氏来島の際、土地問題を本村の基本的重要問題として直訴した。キャラウェイ氏は要請を受け入れ、島の土地問題は米国民政府土地裁判所において審議することとなり所有権の帰属について係争が続けられた。
昭和39年7月30日、高等弁務官の採決に当事者が合意し、1,679ヘクタールの農地は無償で農民に所有権が認められた。一方残余の宅地等は、大日本製糖会社から琉球政府に条件付き寄贈され、後に琉球政府から村が条件付贈与を受け、村は各使用者に売り渡した。
村民の悲願であった土地所有権問題は、ここに開拓創始以来から、64年6ヶ月8日目にして解決した。
=========================
文化センターの脇にはキャラウェイの銅像もある。
キャラウェイは、日本への沖縄返還反対論者として知られ、当時の沖縄住民の多くが彼に反発していたのだが、大東島民にとっては恩人。人間や事象の評価というのは、ひとつの方向からだけでは解らないものである。
その後、役場に寄り南大東村史を買いに行き(長男が)、ふたたび怪しい自転車隊金城1号金城2号は島の真ん中へ移動。

3日目にして思ったのだが、この島を自転車で回るのはけっこう大変だ。
そうはいいながらも午前中、島まるごと館(入館料200円、今回はちゃんと小銭を持っていった)と、ラム酒工場「グレイスラム」、そして、長男の強い要望により秋葉神社の近くにある忠魂碑へと精力的に金城1号金城2号は走る。
島まるごと館では、館の人に「自転車で島を回ってるんですか」とびっくりされる。やっぱり島の人から見るとそうなのだろうなぁ。
旧空港にあるラム酒工場「グレイスラム」で見学をしたのだが、ラム酒のことはそっちのけで旧空港の施設がいろいろ残っているのにびっくりする。


建物は旧空港をそのまま利用 中に入ってもそのまま


奥の工場に入ってもそのまま 昔は18人乗りだった
12:30頃
昨日同様大東そばを昼に食べ、民宿に戻ってきた。
あとはシャワーを浴び、飛行機出発の時間までゆっくりして土産などを買いに集落をうろうろしようと思っていた。
7:00過ぎ起床。
やや昨日の酒が残っている。結局、今日も朝日は見にいけなかった。。。
8:00
朝を軽く食べ、気象台へ行く。
台風の時に良く聞く南大東島。
ここの気象台は台風観測の最前線であるとともに、高層気象観測を行っている。
高層気象観測とは高度約30km付近(成層圏)までの気圧、気温、風光、風速を観測するもの。ここから得られたデータにより高層天気図を作成し天気予報に利用したりしている。こういった観測所は日本国内では16か所、全世界には約900か所あるという。
観測方法は気球に水素ガスを充填させ、空へ飛ばす。気球に付けたセンサーで観測し情報を送ってくるという仕組み。1日に2回、8:30と20:30に観測しているという。気球を飛ばすのは自動化されているので、人手は気球の補充くらいしかいらないという。
水素ガスが入る前の気球 センサー
と、いった説明を気象台の人に受け、さぁ観測時間(気球が飛び出す時間)の8:30になった。
8:30
気球がポンと飛び出し、一気に飛んでいく。あっという間に空の彼方へ飛んでいった。
気象台の近くにあった、ふるさと文化センター(入館料200円)に入る。
この島はその昔、島全体が製糖会社の社有地だったということは知っていたが、以下のような土地問題があったことを初めて知った。
=========================
南大東の土地問題~土地所有者認定記念之碑より抜粋~
本村の農地は、明治33年以来、国有地であった原生林を玉置商会が借り受け、同商会と開拓農民との間に貸付期間満了後は農民に所有権が払い下げられるとの口約で、前人未到の地に、農民の自力自費を投じて指南にして崇高な開拓がすすめられ、大将の初期には全農地が開拓された。
大正5年、経営不振に陥った玉置商会は、事業権を東洋製糖株式会社に売り渡し、諸々の経緯を経て東洋製糖会社は土地の所有権も取得した。しかし昭和3年、同社は大日本製糖株式会社に合併されたため、南大東島は大日本製糖株式会社の所有地となった。結果、島は位置会社が経営支配するという日本国中に前例のない社会制度が昭和21年まで続いた。
昭和26年、農地の所有権は開拓農民およびその後継者にあるという先の事実に基づき、村長以下全村民が団結して、土地所有権認定問題を関係当局に提起。会社とも折衝を重ねたが、島の支配者も変転されているだけに困難を極めた。昭和36年6月、時の琉球列島高等弁務官キャラウェイ氏来島の際、土地問題を本村の基本的重要問題として直訴した。キャラウェイ氏は要請を受け入れ、島の土地問題は米国民政府土地裁判所において審議することとなり所有権の帰属について係争が続けられた。
昭和39年7月30日、高等弁務官の採決に当事者が合意し、1,679ヘクタールの農地は無償で農民に所有権が認められた。一方残余の宅地等は、大日本製糖会社から琉球政府に条件付き寄贈され、後に琉球政府から村が条件付贈与を受け、村は各使用者に売り渡した。
村民の悲願であった土地所有権問題は、ここに開拓創始以来から、64年6ヶ月8日目にして解決した。
=========================
文化センターの脇にはキャラウェイの銅像もある。
キャラウェイは、日本への沖縄返還反対論者として知られ、当時の沖縄住民の多くが彼に反発していたのだが、大東島民にとっては恩人。人間や事象の評価というのは、ひとつの方向からだけでは解らないものである。
その後、役場に寄り南大東村史を買いに行き(長男が)、ふたたび怪しい自転車隊金城1号金城2号は島の真ん中へ移動。
3日目にして思ったのだが、この島を自転車で回るのはけっこう大変だ。
そうはいいながらも午前中、島まるごと館(入館料200円、今回はちゃんと小銭を持っていった)と、ラム酒工場「グレイスラム」、そして、長男の強い要望により秋葉神社の近くにある忠魂碑へと精力的に金城1号金城2号は走る。
島まるごと館では、館の人に「自転車で島を回ってるんですか」とびっくりされる。やっぱり島の人から見るとそうなのだろうなぁ。
旧空港にあるラム酒工場「グレイスラム」で見学をしたのだが、ラム酒のことはそっちのけで旧空港の施設がいろいろ残っているのにびっくりする。
建物は旧空港をそのまま利用 中に入ってもそのまま
奥の工場に入ってもそのまま 昔は18人乗りだった
12:30頃
昨日同様大東そばを昼に食べ、民宿に戻ってきた。
あとはシャワーを浴び、飛行機出発の時間までゆっくりして土産などを買いに集落をうろうろしようと思っていた。
Posted by tana at 22:05│Comments(0)
│10.11南大東島へ